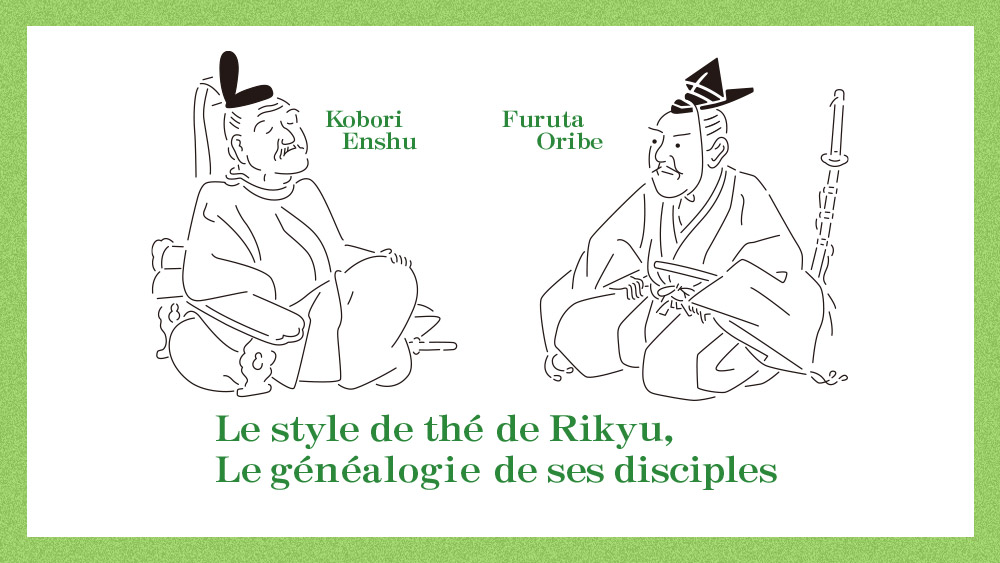
茶の大成者であり、ストイックで強い信念を持っていたであろう利休から茶を習った弟子たちは、師の茶風を忠実になぞったのでしょうか。
ここでは、利休の一番弟子とされる古田織部(ふるたおりべ)、その弟子の小堀遠州(こぼりえんしゅう)の茶の特徴をみつめます。
「へうげもの」古田織部
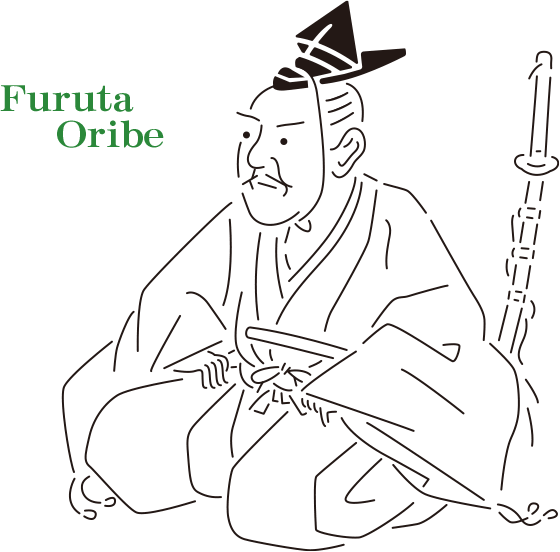
「天下一の茶の宗匠」
秀吉時代に、利休からお茶を習った七人は、後に「利休七哲(りきゅうしちてつ)」と呼ばれます。古田織部(1543〜1615)もその一人です。
織部は、尾張国の武家の生まれで、信長、秀吉のもとで幾多の戦いに参陣し、関ヶ原の戦いでは徳川家康の東軍に加わり、その功績に対する褒美により、一万石の大名となりました。
その後は茶の湯を楽しむ日々を過ごし、二代将軍徳川秀忠の招きで、江戸で茶を指南したことから「天下一の茶の宗匠」と評されるようになりました。
40歳で利休に出会う
織部が利休と出会ったのは、40歳の頃。利休は当時60歳ほどで、交流は亡くなるまでの約10年間続きました。二人は陣中に熱海の温泉へ出掛ける仲で、織部は、利休が京都を追放され堺に下る際には淀の船着き場まで見送りに行き、利休亡き後は利休からもらった茶杓に「泪」と銘を付け、小窓を開けた竹筒に入れ、位牌代わりにしたといいます。互いに相手を想う気持ちは強く、信頼関係も深かったのでしょう。
さぞや織部は、利休の茶風を再現するかのように受け継いだだろうと考えがちですが、実際は違いました。織部の道具は豪快で、なかでも形をあえてゆがませた沓(くつ)形の茶碗を作るあたりには、奔放で前衛的な芸術家気質を見る思いがします。こうした茶碗は「へうげもの(ひょうげもの)」と呼ばれ、人気と注目を集めました。「へうげもの」とは、滑稽なふるまいをしてみせる者、ひょうきん者などの意味です。
織部は茶道具の製作に限らず、建築、作庭など多岐にわたって活躍しました。それらは「織部好(ごのみ)」として、慶長年間(1596〜1615)に爆発的な流行をみせました。
織部は織部でなくてはならない
利休は、作為なくゆがんでしまった茶碗からも美を感じ取っていたようです。それに対して、織部は明らかに茶碗をゆがませています。この差について、映画『利休』(監督:勅使河原宏、1989年)の脚本を共同執筆した赤瀬川原平氏は、「無作為を手法として守って、利休と同じことをしていれば、それは利休的精神をますます離れていくことになるだろう。そうではなくて、織部は織部でなくてはならない。そして織部は茶碗をぐいぐいと歪ませていったのである。」と分析しています。

格子や渦巻などの文様が描かれた黒織部
織部は、点前でも特定のルールにこだわらなかったようです。右手に高麗茶碗、左手に建水(けんすい:茶碗を清めたり温めたりするときに使った湯や水を捨てるために使う道具)を持って現れたかと思えば、ある時は唐津茶碗だけを持ち、またある時は左手に建水に入れた茶碗を持ってきたとの記録があります。
時の移るによりて改むること
織部の茶の湯は、なぜ、このような個性を放ったのでしょうか。織部の研究で知られる久野治氏が記した『新訂 古田織部の世界』によると、織部が青年期から22年間仕えた信長の影響がありそうです。信長は、ポルトガルから伝来した鉄砲をいちはやく入手するなど、ヨーロッパ文明を大胆に採り入れました。その薫陶を受けていたと考えるのは自然でしょう。
織部は、天下泰平を謳歌する桃山時代が訪れたことを好機とし、豊かな感性と大胆かつ斬新な発想を茶の世界にも注いだのでしょう。「茶の道は時の移るによりて改むることなり」。織部が残したこの言葉に、織部の茶は収れんされているように思えます。
「きれいさび」小堀遠州
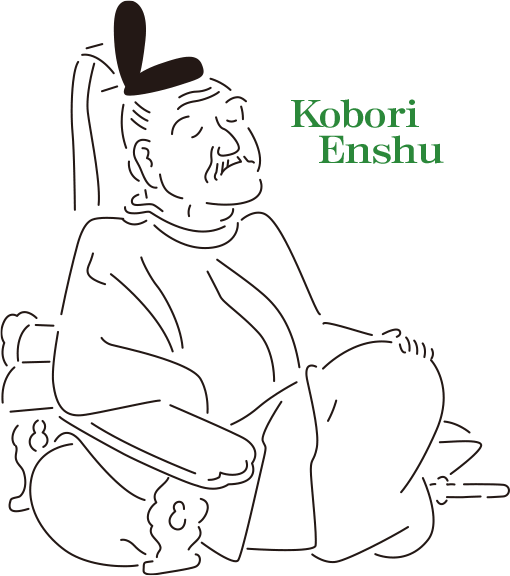
徳川将軍家の茶道の指南役
利休の一番弟子、古田織部に師事した小堀遠州(1579〜1647)は近江国の生まれで、戦国時代から江戸時代の武将です。幼い頃から英才教育を受け、珠光、武野紹鷗、千利休、古田織部と続いた茶の湯の本流を受け継ぎ、徳川将軍家の茶道指南役となりました。
10歳で利休、16歳で織部と出会う
遠州は10歳の頃に利休に会ったといいます。秀吉が奈良の郡山へお成りの際、遠州が給仕役を務めたからで、その前日には利休が秀長に茶を教えている様子も見ていると語っています。
この前年には、京都北野天満宮境内において秀吉が催した大規模な茶会、北野大茶会が行われました。この茶会は当時の耳目を集めたこともあり、遠州も子どもながらに茶道への関心を高めていたのでしょう。
遠州は16歳で父に伴われて茶会に臨みます。住まいが織部の屋敷の近くだったその頃に、織部の門に入ったとみられています。当時は、現代のように稽古があるわけではなく、師の茶会の客になったり、師と共に茶会に行ったり、あるいは、自身の茶会に師を招いたりする中で、教えを身に付けるものだったようです。
遠州が織部から茶の湯を学んだのは約10年というのが通説です。織部は、吉野山で花見を行い、利休を追悼する場へ遠州を連れて行きました。遠州は、ある藩主が家臣に織部の茶の湯を尋ね、その返答をまとめた書を自ら写しています。師弟である二人の交流もまた、利休と織部のそれと同じく深いものだったと想像できます。
茶の湯に王朝、海外の要素を融合
遠州の茶風は、「きれいさび」と称されます。独自の美意識は江戸時代を通じて多くの大名、文化人に影響を与え、現在まで継承されています。
遠州が40代から60代を過ごした寛永年間は、文化人たちがサロンを形成し、公家、武家、町衆、文人などが身分を超えた交流を通して新たな美的感覚を醸す寛永文化を生みました。遠州は、後水尾(ごみずのお)天皇のサロンの中心的人物であり、また、伏見奉行という立場から長崎を経由する海外の最新情報を知り、様々な異文化に深い関心を持っていました。
こうした出会いから、遠州は王朝文化と海外文化の優れた要素を独自の審美眼と感性で茶の湯の世界に融合・調和させ、「きれいさび」という独特の世界を創り上げたと評されています。
遠州好みの茶入は「中興名物」と呼ばれています。国内各地の窯で焼かれた茶入に、和歌にちなんだ銘を付けたり、箱などの附属品に蒔絵などで文字を入れたものが挙げられます。そうした遠州の試みは、茶の湯に新たな貴族趣味を融合させたとも語られています。
侘びの世界に、客観性の美を
遠州を語る上では、作事奉行で活躍したことも外せないポイントです。桂離宮、仙洞御所(せんどうごしょ)、二条城、名古屋城、大徳寺孤篷庵(だいとくじこほうあん)、南禅寺金地院(なんぜんじこんちいん)などの築城、建築、作庭を指導したほか、書画・和歌・美術工芸品の指導、鑑定にも秀でていました。特に美術工芸の面においては、高取焼(たかとりやき)、丹波焼(たんばやき)、信楽焼(しがらきやき)、志戸呂焼(しとろやき)、伊賀焼(いがやき)などの茶陶の指導にも偉大な足跡を残し、中国、朝鮮半島、オランダ、東南アジアなどへの茶陶の注文にも力を注ぎました。

染付茶碗は海外で焼かれたものも多い
国際感覚を持ち、多くの分野で天賦の才を発揮した遠州は、日本を代表する総合芸術家であり、日本のレオナルド・ダ・ヴィンチとも称賛されています。教養豊かで文化に造詣が深かった遠州は、精神性を追求した侘びの世界に、誰もが楽しめる客観性の美を取り入れたといっていいでしょう。
特集「利休、二つの系譜」目次
ルピシアの抹茶
「茶道」から学ぶことは様々。相手をもてなす「心」はもちろん、なにより自分自身が楽しむ「心」も大切ですね。ルピシアでは気軽に「抹茶」を楽しめる商品をご用意しています。
≫ ルピシアの抹茶はこちら
 LUPICIA Tea Magazine
LUPICIA Tea Magazine