
お茶にまつわる江戸時代の日常茶飯と、四季の風情。7枚の浮世絵がご案内します。
監修および画像提供/ 入間市博物館
「餅酒二偏嘉世意の多多買」
歌川広重 初代 天保14~弘化4年(1843~1847年)
擬人化された餅(茶)と酒(魚)が戦いを繰り広げるという趣向の作品。茶の道具として、茶釜、土瓶、急須、やかんなどのほか、茶台、茶托などの小道具が描かれ、茶壺や紙袋に詰められたさまざまな銘柄の茶までが参戦している。

「江戸名所百人美女 浅草寺」
歌川豊国 三代 安政4年(1857年)
前掛けは、茶店の女性のシンボル。この絵では茶碗に注がれたお茶の色も見える。

「東都名所 亀戸藤花」
歌川広重 初代 天保2年(1831年)
亀戸天神の茶店。亀戸天神の藤は江戸の名所の一つ。茶店の道具立ては、茶釜の上にやかんがのるというもの。

「たけこ(養蚕の図)」
歌川国明 安政4年(1857年)
養蚕の作業の合間に土瓶に入ったお茶を飲む。
女性が運ぶ盆の上の茶請けは漬け物?

「山本茶店前美人」
歌川国芳 弘化頃(1845~1848年)
山本嘉兵衛は、初めて狭山茶の取り引きを行った茶商。天保6年(1835)に覆下(おおいした)茶園の茶葉を使った蒸し製煎茶「玉露」の製法を創始したと伝えられる。
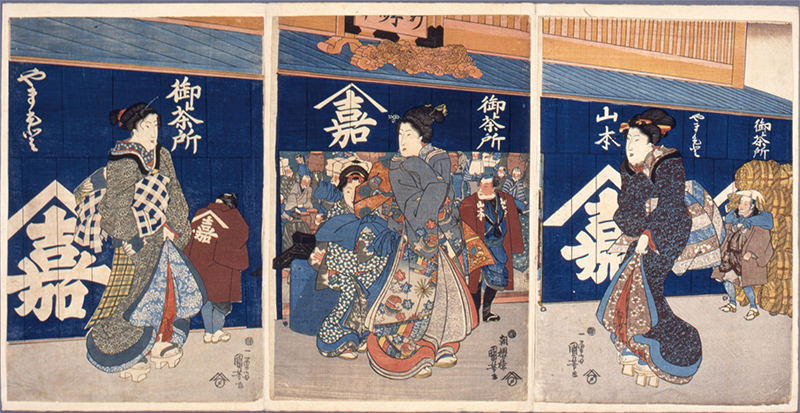
「お仙の茶屋」
勝川春章 明和頃(1764~1772年)
笠森お仙を描いた作品。三宝にのっているのはお供え用の団子。この作品には描かれていないが、お仙を同時代に描いた作品では、茶釜から煮出したお茶を茶碗に注ぐ場面などが描かれている。
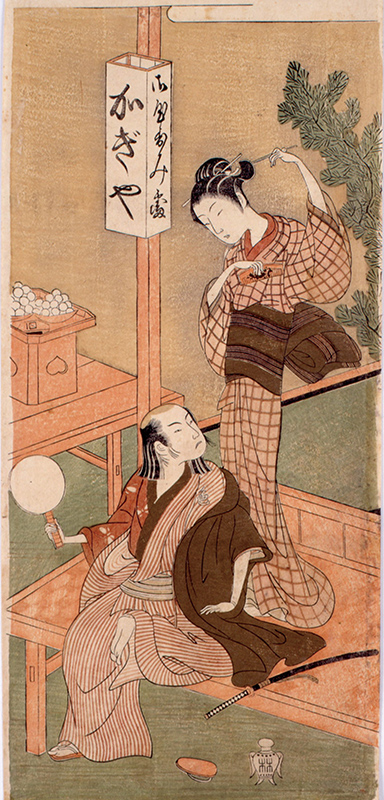
「新撰江戸名所 高輪二十六夜之図」
歌川広重 初代 天保頃(1830~1844年)
東海道の第一の宿場・品川の手前に位置する高輪。間近に江戸湾を望む場所には、多くの水茶屋が並んでいた。ことに二十六夜(7月26日)には、月見の人々でにぎわった。

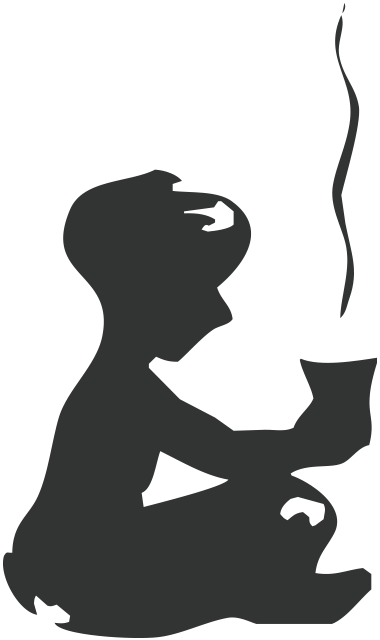 LUPICIA Tea Magazine
LUPICIA Tea Magazine


