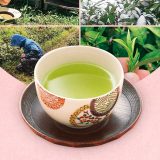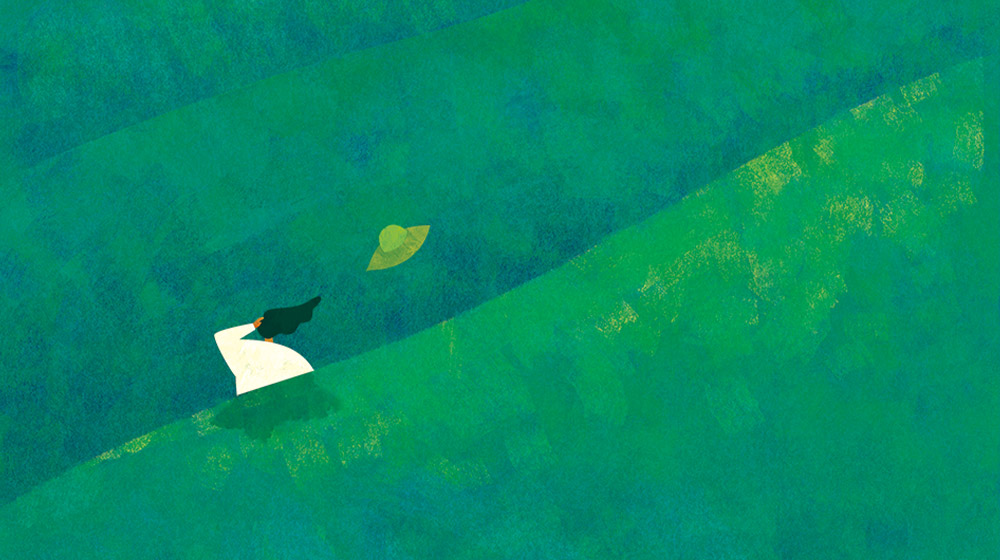
新茶前線、北上中!
山々に、そして街路樹にも、芽吹きの季節がやってきました。春風とともに種子島からスタートした日本の新茶前線は、鹿児島、静岡と徐々に北上し、いよいよシーズン本番を迎えました。
新茶とは、その年最初に発芽した新芽で作られるお茶のことで、一番茶、一番摘み、初茶とも呼ばれます。そこから収穫順に、二番茶、三番茶、四番茶と数えられます。日本だけでなく、紅茶では一番茶をファーストフラッシュ、烏龍茶では春摘み茶と呼ぶなど、ニルギリ、ダージリン、台湾をはじめ世界中のお茶産地も順に旬を迎えていきます。
若葉の清々しい香り、冬を乗り越えて蓄えたエネルギーがぎゅっと凝縮された濃厚な旨み、旬の鮮度感を味わえるのは、新茶だけが持つ最大の魅力。各地から次々と到着する多彩な新茶に目移りしてしまいますね。
「新茶到来!品種でお茶を味わう。」目次
お茶の品種ってご存じですか?
香りで選ぶ、味で選ぶ、産地で選ぶ。自分にぴったりの新茶を探すとき、お茶の「品種」を意識したことはありますか? お米に「コシヒカリ」や「あきたこまち」などの品種があるように、日本茶にも「やぶきた」、「さえみどり」など多様な品種があることをご存じでしょうか。「日本茶」とひと口にいっても、その味わいや香り、水色は「品種」によって大きく異なります。現在、公式に登録されている日本茶の品種は120種以上あり、今もなお新しいお茶が誕生し続けているのです。
「品種」を知ることで、茶葉それぞれが持つ個性や違いをこれまで以上に実感できることでしょう。ぜひ、自分好みのお茶を探す道標のひとつとして品種にも注目してみてください。お茶のおいしさ、味わい方、楽しみ方を広げて、この春理想のお茶に出会えますように。
品種についてー茶樹の系統の基本と味わいー
お茶といえば緑茶、烏龍茶、紅茶などの種類があることはよく知られていますが、それらの原料がすべてカメリア・シネンシスという「チャの木の葉」であることをご存じでしょうか。発酵させる度合いの違いによって緑茶や紅茶、烏龍茶へと違うお茶に姿を変えるチャの木の葉ですが、それぞれのお茶に適した原料として栽培されているのは、その葉の大きさや樹木の高さなどから、2種類に大別されます。
小葉種(しょうようしゅ)
中国種:低木茶
葉の長さ3~5㎝ 主に温帯地域で栽培
風味の特徴:旨み、繊細な香り。アミノ酸が多く、耐寒性に優れている。
(主に緑茶・烏龍茶)

ひとつは小葉種。葉が小さく樹高が低いことが特徴です。比較的寒さに強く、シャープな味わいで香気に優れていることから、主に緑茶や烏龍茶の原料になります。お茶の起源である中国、また日本、台湾などで古くから栽培される伝統的な品種。19世紀に英国のロバート・フォーチュン(※)によって、中国からインドへ運ばれたこの茶樹とその子孫がダージリンに根付いたこともあり、主に紅茶の世界では中国種(チャイナ)とも呼ばれ、寒暖差のある高山などで栽培されています。
※ロバート・フォーチュン:1812~1880年 スコットランド生まれ。中国からインドへ、茶樹を持ち出したことで有名なプラントハンター、植物学者、商人。

大葉種(だいようしゅ)
アッサム種:高木茶
葉の長さ10~18㎝ 主に亜熱帯・熱帯地域で栽培
風味の特徴:コクのある濃厚な風味と渋み。タンニンが多く、アミノ酸が少ない。
(主に紅茶)
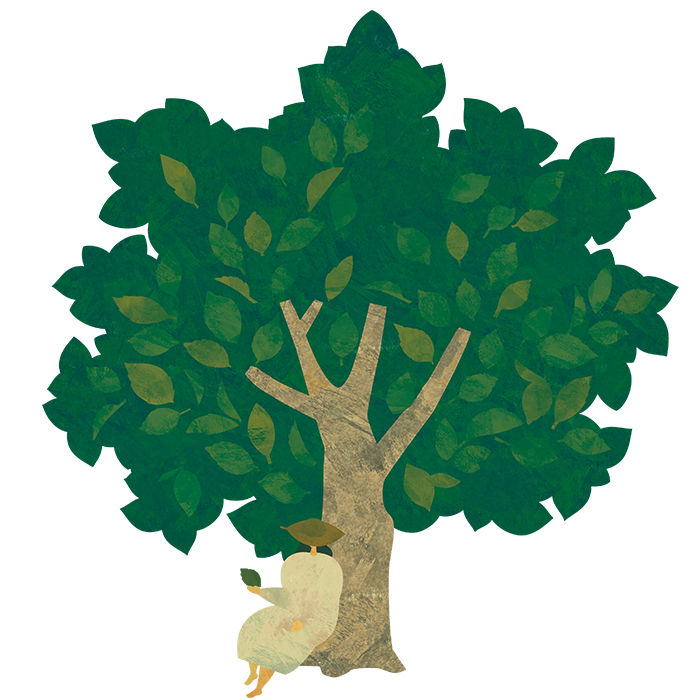
もうひとつは大葉種。葉が大きく、樹高10mを超える大木に育ちます。温暖な気候を好み、渋みの成分であるタンニンの含有量が多く、主に紅茶の原料になります。インド東北部から中国雲南省にかけて自生し、1823年にインドのアッサム地方で発見されたことから、紅茶の世界ではアッサム種と呼ばれています。インド、セイロン(スリランカ)、ケニアなどの多くの紅茶産地では、アッサム種を栽培しています。
クローナル種とは?
クローナル種
風味の特徴:香気、風味に優れる均一な味わい。
母樹によって特徴は異なる。
(緑茶、紅茶、烏龍茶などお茶全般)
中国種、アッサム種とともに、現代の茶樹栽培の主流となっているのがクローナル種。優良品種の母樹から、葉または枝などを収穫し、挿し木や挿し葉でクローンとして増やしたものです。収穫期や風味が均一であるため管理しやすく、また優れた遺伝子を選抜しているため、風味の傾向が出やすいなどのメリットがあります。「やぶきた」などの日本茶の品種も、基本的に挿し木で栽培したクローナル種です。

お茶を品種で楽しむ
小葉種(中国種)と大葉種(アッサム種)、クローナル種の中に、さらに日本茶、紅茶、台湾茶、それぞれの個性を引き出す、だくさんの品種が生まれてきました。ここでは、到着したばかりの日本新茶をはじめ、これから旬を迎えるダージリン、台湾茶の代表的な品種をご紹介します。
日本茶
秋冬にぎゅっと蓄えたエネルギーが凝縮した、香り、旨み、甘みの頂点に達する日本新茶の醍醐味を、お気に入りの品種でお楽しみください。

やぶきた
旨みと香りに優れる日本茶の王様
日本茶の約7割を占める、日本茶の代名詞的な品種。杉山彦三郎氏が静岡県の在来種から選抜し、静岡県茶業試験場で育成。藪(やぶ)を切り開いた茶園の北側に植えた茶樹から選抜したことから、「やぶきた」の名前が付いたといわれています。
あさつゆ
際立つ個性的な甘い香り
京都宇治の在来種から選抜されたもの。栽培管理が難しい反面、茶葉の色艶や優れた滋味など、品質において高い評価を受けており、天然玉露とも呼ばれています。愛好家の多い人気品種です。
ゆたかみどり
若草を思わせる豊かな香りと滋味
「あさつゆ」から生まれた、ほっこりとした風味の早生品種。「やぶきた」に次ぐ栽培面積で、鹿児島が主な産地。茶葉の色艶も評価の高い品種で、ハーブや若草を思わせる個性的な芳香が特徴。
さえみどり
気品のある香気と爽やかな風味
1969年に「やぶきた」を母親に、「あさつゆ」を父親として交配した中から選抜された品種で、耐寒性はありますが、早生品種である特徴を活かすために暖地、温暖地での栽培が推奨されています。
蒼風(そうふう)
青みのある花香にも似たキレ味
「やぶきた」を母に、インドから運ばれた紅茶品種「印雑(いんざつ)131」を父に持つ品種であり、釜炒り緑茶、烏龍茶に適した品種としても知られています。「やぶきた」の青々とした清涼感と「印雑131」の藤やジャスミンの花を思わせる華やかな香りが特徴です。
ダージリン
19世紀から続く伝統的な紅茶の名産地
インドのダージリンで本格的な紅茶栽培が開始されたのは1852年。中国武夷山から持ち込まれた茶樹の苗木を植樹したことに始まります。この時の子孫は中国種と呼ばれ、爽やかな滋味と香り高く自然な香気が特徴です。また、夏摘み紅茶は伝統的に中国種のみとされ、特有のマスカテルフレーバーが特徴です。
近年、ダージリンの栽培の主流を占めるようになったクローナル種は小葉種と大葉種、これらを交配させた交雑種(ハイブリッド)の中から、特に品質や耐病性、収量などにすぐれた茶樹を選抜し母樹にしたもの。なかでも主要名園を代表するスペシャルティーとして使われている「AV2」は、花のように甘い圧倒的な香りと、みずみずしく繊細な風味で有名です。
台湾茶
烏龍茶の名産地を品種で味わう
台湾茶で有名な烏龍茶も「小葉種」で作られています。
台湾茶の名称の基本構成は「地名+品種」。「阿里山金萱(アリサンキンセン)」なら、「阿里山」で作られた「金萱種」のお茶を意味しますが、青心烏龍(チンシンウーロン)は単に「烏龍」で示されます。ほかに、新品種の金萱、翠玉(スイギョク)、四季春(シキシュン)などの特徴を押さえれば、購入時に迷うことはないでしょう。
「青心烏龍」は台湾で最も歴史が古い品種の一つで広範囲に分布しており、烏龍といえば、基本的に青心のことをいいます。「金萱」は、台茶12号の別名です。台湾茶業改良場で育成された品種でミルキーな甘い香りが魅力。正式名称が台茶13号の「翠玉」は、青みが強く、ジャスミンのような花香が特徴です。「四季春」は、1年に6回収穫できるほどの強靭さで、爽やかな風味があり、台湾茶らしい緑の味わいを手軽に楽しめる、人気の品種です。
「新茶到来!品種でお茶を味わう。」目次
日本新茶2025
南北に伸びる日本列島では、3月から5月にかけて新茶前線が南から北へ移動。ルピシアは新茶前線を追いかけ、いち早くご紹介していきます。
≫ ルピシアの日本新茶はこちら
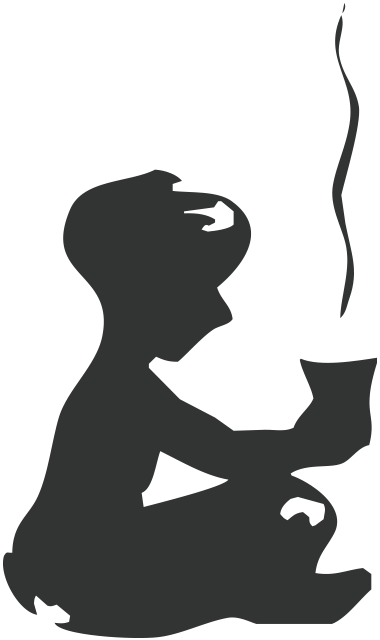 LUPICIA Tea Magazine
LUPICIA Tea Magazine